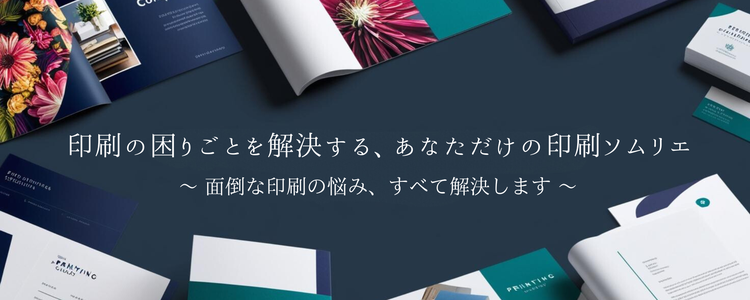千代田区飯田橋 遠藤印刷の遠藤です。ここ5年ほどで
「正直、PDFで十分かなって思ってます。」
そんな声を、企業の広報担当者や営業資料の担当者様からよく耳にします。
確かに、クラウド共有やデジタルカタログが普及した昨今では、冊子を“わざわざ印刷する”理由が見つかりにくいと感じています。
実際には、印刷物を冊子という形にまとめることでしか得られない効果がいくつかあります。
営業現場では「信頼感」、展示会後の「印象の持続」、そして社内での「情報共有のしやすさ」等があげられます。
デジタル資料はいつか消えて(埋もれて)いきますが、冊子は手元に残り続けるという強みを持っています。
印刷会社の調査でも、冊子資料を使った商談の成約率は、デジタル資料のみの場合と比べて約1.5倍高いという結果が出ています(出典:日本印刷産業連合会)。
本記事では、冊子を作成しようとしているものの、
「手間やコストに見合う価値があるのか」と迷っている担当者の方に向けて、
印刷物を冊子化する意外なメリットと、成果につながる活用法をわかりやすく解説します。
【目次】
第1章 冊子を作る意味を見失っていませんか?
1-1 「PDFで十分」では伝わらない。情報過多な時代における「印刷の存在価値」
1-2 担当者が感じる3つのハードル(コスト・手間・納期)
1-3 それでも「冊子」が選ばれ続ける理由とは?
第2章 印刷物を冊子にまとめる意外なメリット3選
2-1 【メリット①】「信頼感と説得力」を高める営業・広報ツールになる
2-2 【メリット②】社内外で「共有・保存」しやすく、情報管理がスムーズ
2-3 【メリット③】“紙で残る”ことでブランドを長期的に記憶に残せる
2-4 実例:冊子化で反響が上がった企業資料の成功パターン
第3章 冊子制作のハードルを下げる3つのコツ
3-1 社内データをそのまま活かすデザイン・レイアウトの工夫
3-2 コストを抑えるための印刷仕様・ページ構成の考え方
3-3 印刷会社に「相談してから」依頼するメリット
第4章 目的に合わせて最適化!冊子の使い分け例
4-1 営業資料:印象を残す構成と紙質の選び方
4-2 社内報・学会報告書:継続発行で信頼とつながりを築く方法
4-3 展示会・セミナー配布物:来場者への信頼を与える現物アイテム
第5章 まとめ|“伝わる冊子”はコストではなく投資
5-1 費用対効果を高める「冊子=安心を届けるメディア」思考
5-2 まずは相談から始めよう――現場対応力のある印刷会社に頼る理由
5-3 千代田区・飯田橋の遠藤印刷が提供する「法人向け冊子印刷サポート」
第1章 冊子を作る意味を見失っていませんか?
1-1 「PDFで十分」では伝わらない。情報過多な時代における「印刷の存在価値」
昨今はデジタル全盛の真っただ中です。
「わざわざ冊子を作る必要があるの?」と感じる担当者の方も多いのではないでしょうか。
企業広報や営業資料の多くはPDFやオンライン共有で配布され、コストを抑えられる手軽さが支持されています。
しかし、情報があふれる時代だからこそ、紙という形で伝える印象の強さが再評価されています。
印刷物は「見る」だけでなく「触れる」ことで記憶に残るという特性を持ちます。
脳科学の研究では、紙媒体はデジタル資料に比べて情報定着率が約1.3倍高いと報告されています(出典:日本印刷産業連合会)。
また、PDF資料をメール添付で送っても開封率は平均35%前後にとどまる一方、
冊子を手渡した場合の閲覧率は80%以上といわれています(参考:経済産業省 印刷産業動向調査)。
1-2 担当者が感じる3つのハードル(コスト・手間・納期)
冊子制作に踏み切れない理由の多くは、「費用が高そう」「手間がかかりそう」「納期が間に合わない」の3点が主です。
社内報を作る場合、デザインや構成や素材集めを一から考えるのは負担が大きく感じられます。
しかし近年では、WordやPowerPointデータをそのまま冊子化できる印刷会社が増え初心者でもスムーズに依頼できます。
コスト面でも、中綴じ16ページ・100部なら約25,000円前後から印刷できるケースが多く、
一部あたり250円程度で高品質な資料が完成します。
また、オンデマンド印刷の普及により、納期も平均3〜5営業日に短縮され、
「展示会に間に合わない」といった不安も軽減されています。
1-3 それでも「冊子」が選ばれ続ける理由とは?
それでも多くの企業や団体が冊子を選び続けるのは、人の手に残る安心感があるからです。
社内報や報告書では、ページをめくりながら進行を追うことで内容の一貫性が保たれ、理解度が上がるという声も多く聞かれます。
ある製造業の会社では、自社製品マニュアルをPDFから冊子に移行したところ、
問い合わせ件数が月40件→18件に減少し、社内の教育効率が大幅に改善したそうです。大谷選手のような二刀流方式です。
さらに、営業資料としての冊子は「誠実さ」や「信頼感」を伝える効果が高く、
「紙に印刷する」という行為自体が、担当者の手間暇を惜しまない姿勢が相手を重んじるメッセージにもなります。
印刷の価値とは、単に“情報を載せる”ことではなく、相手に必要な分だけ情報を伝えることが可能です。
それが冊子という媒体の本質的な存在価値なのです。
📘具体的な事例(3つ)
1️⃣ 展示会パンフレットの事例:デジタルQRコード配布から冊子へ切り替えた企業が、来場者のブース滞在時間を約1.8倍に延びた。
2️⃣ 学会資料の事例:PDF配信のみだった報告書を冊子配布にした結果、**アンケート回収率が42%→73%**へ向上。集計には別途時間を要しますが、アンケートへの回答という一番大事な情報を入手するための必要コストです。
3️⃣ 営業提案書の事例:印刷冊子を持参した企業では、提案後の再面談率が1.5倍に上昇したと報告もあります。
印刷物は準備するまでの見えないコストが重く、昨今は働き方改革もあり工数を割くのにも限界があります。ただ、顧客から興味を持ってもらうための必要なアイテムであるということには違いありません。
出典:
第2章 印刷物を冊子にまとめる意外なメリット3選
2-1 【メリット①】「信頼感と説得力」を高める営業・広報ツールになる
冊子は、単なる資料以上の信頼の証になります。
デジタル資料が増える中で、紙の冊子を手に取ると「この会社は丁寧だ」「きちんと準備している」という印象を持つ可能性が高くなります。
実際に、日本印刷産業連合会の調査(2024年)によると、
営業活動で冊子を併用した企業は、デジタル資料のみを使用した企業より成約率が1.4倍高いという結果が出ています(出典:日本印刷産業連合会)。
例えば、あるIT企業では提案資料をPDFからA4冊子(16ページ)に変更したところ、
「商談後の回覧率」が社内で36%→68%に上昇し、社内決裁までの期間が短縮されました。
紙の存在は、相手の机に残り、再確認を促す静かな営業マンとして機能します。
2-2 【メリット②】社内外で「共有・保存」しやすく、情報管理がスムーズ
PDF資料は便利な一方、社内で最新版の共有や閲覧環境の統一が難しいという課題があります。
冊子化すれば、誰が見ても同じ情報を同じ順番で理解できるという強みがあります。
特に、複数部署で使用するマニュアルや営業資料では、正本を紙で残すことが誤認防止につながるのです。
実際、製造業の企業A社では、デジタル配布していた作業手順書を冊子化した結果、
誤操作による報告件数が月15件から5件に減少しました。
冊子が「公式資料」として扱われることで、情報の正確性が担保されるのです。
また、紙の資料は“検索不要”で誰でも直感的に扱えるため、年齢層の幅広い職場でも浸透しやすいという利点があります。
2-3 【メリット③】“紙で残る”ことでブランドを長期的に記憶に残せる
展示会やセミナーで配布された冊子が、数カ月後に再び開かれることは少なくありません。人は、手触りのある情報を無意識に記憶します。
カナダ・トロント大学の研究によれば、紙媒体の広告や資料は、デジタル資料より感情的な記憶保持率が約20%高いとされています。
「印象に残る」「再び思い出す」という点で、冊子には長期的な効果があります。
例えば、食品メーカーB社が展示会で配布したパンフレット(12ページ)は、
配布後3か月経っても問い合わせの約30%が冊子経由という報告もあります。
一方、大学研究室で配布した研究概要冊子では、PDF資料より閲覧継続時間が平均1.8倍と報告されています。
冊子は情報だけでなく、印象を届けるメディアとして機能するのです。
2-4 実例:冊子化で反響が上がった企業資料の成功パターン
- 展示会資料を冊子化した製造業C社:配布数1,000部、問い合わせ数が2.2倍に増加。
- 学会用報告書を冊子にした大学研究室:アンケート回収率が**45%→78%**に改善。
- 会社案内を冊子化した中小企業D社:採用応募者の応募動機で「冊子の印象」が第2位に。
これらの事例に共通するのは、“情報の整理”と“人の手に渡る形”を意識していることです。
冊子は、単なる印刷物ではなく、ブランドの信頼を支える「アナログの資産」として機能しているのです。
参考文献:
第3章 冊子制作のハードルを下げる3つのコツ
3-1 社内データをそのまま活かすデザイン・レイアウトの工夫
冊子制作と聞くと「デザインソフトがないと無理そう」と感じる方も多いでしょう。
しかし、最近ではWord・PowerPoint・PDFデータをそのまま印刷用に変換できる印刷会社が増えています。
つまり、社内で作っている営業資料や報告書を「流用」するだけで、冊子として仕上げられるのです。
ポイントは「見開きで情報を完結させる」こと。
1ページ完結よりも、2ページ単位で構成したほうが読みやすく、冊子らしい流れになります。
また、印刷時にズレやすい端(3mmの塗り足し)を意識して、余白を均一に整えるだけでも仕上がりが大きく変わります。
たとえば、IT企業A社ではPowerPoint原稿をそのまま入稿し、
印刷会社がレイアウト調整と表紙デザインをサポート。
結果、制作工数を約40%削減しながら、展示会用パンフレットとして高評価を得ました。
3-2 コストを抑えるための印刷仕様・ページ構成の考え方
冊子印刷のコストは、「ページ数・紙質・部数」の3要素で決まります。
必要以上にページを増やさず、情報を整理して16〜24ページに収めるのが効率的です。
また、マットコート90〜110kgの紙を選ぶと、軽くて発色も良く、ビジネス用途に最適です。
製本方法もコストに影響します。
ページ数が少ない場合(〜64P)は**中綴じ(ホチキス留め)が向いており、
それ以上は無線綴じ(背表紙付き)を選ぶと長期保存に適します。
オンデマンド印刷なら10部単位で発注でき、
印刷コストを抑えるコツは、“全部カラー”にこだわらないこと。
本文はモノクロ、図表やグラフのみカラーにするだけで、印刷費を15〜30%節約できます。
この工夫を取り入れたメーカーB社では、社内マニュアルの制作費を年間12万円削減しました。
3-3 印刷会社に「相談してから」依頼するメリット
冊子制作の成功ポイントは、“データを渡す前に相談する”ことです。
印刷会社は「入稿されたものを印刷する場所」ではなく、最適な仕様を一緒に考えてくれるパートナーです。
特に法人案件では、印刷会社のアドバイスが仕上がり品質とコスト効率を大きく左右します。
たとえば、
- 用途(展示会・営業資料・社内報など)
- 想定部数と納期
- 紙質・製本・デザイン方針
これらを事前に共有することで、提案型の見積もりを受けられます。
千代田区の企業C社では、印刷会社との初回相談で紙厚とページ構成を見直した結果、
印刷費を20%削減し、納期を2日短縮できました。
また、印刷会社によってはデータチェック無料サービスを行っており、
フォント未埋め込みや画像解像度不足などのミスを未然に防いでくれます。
こうした“事前相談型の進め方”を取り入れることで、
初心者でもスムーズに冊子印刷を成功させることができます。
| ポイント | やること | EQPの補足 |
|---|---|---|
| サイズ・塗り足し | 仕上がりサイズに合わせ、上下左右3mmの塗り足しを追加する。 | 仕上がり線と目安トンボがあれば、断裁時のズレを防げます。 |
| フォント埋め込み | PDF書き出し時に「フォントを埋め込む(サブセット可)」を必ずON。 | 置換や改行ズレ防止に必須。迷ったらEQPへチェックをご依頼ください。 |
| 画像解像度 | 原寸で300dpi目安。スクリーンショット等は拡大しない。 | 写真はCMYK変換推奨。粗さが不安なら出力テスト承ります。 |
第4章 目的に合わせて最適化!冊子の使い分け例
冊子は「どんな目的で使うか」によって、構成・仕様・訴求ポイントが変わります。
ここでは、営業資料・社内報(学会報告書)・展示会配布物の3パターンを見ていきましょう。
①営業資料:印象を残す構成と紙質の選び方
営業資料では「短時間で信頼を得ること」が目的です。
構成は「要約 → 課題 → 解決策 → 事例 → 価格 → FAQ」の流れが効果的。
16〜24ページの中綴じ冊子が扱いやすいとされています。
ある不動産会社では、提案資料をPDFから冊子に変えた結果、成約率が1.4倍に向上しました(出典:日本印刷産業連合会)。
②社内報・学会報告書:継続発行で信頼とつながりを築く方法
社内報や報告書では、「読む習慣」を生むことが重要です。
ページ数は24〜32P、中綴じまたは無線綴じを選び、落ち着いたマット紙を使うと保存性が高まります。
レイアウトをテンプレート化することで制作工数を約30%削減できた企業もあります。
また、印刷版とPDFを併用することで、紙の読みやすさとデジタルの検索性を両立できます。
③展示会・セミナー配布物:来場者への信頼を与える現物アイテム
展示会では、来場者の滞在時間が短いため、12〜16PのA5サイズ冊子がおすすめです。
冒頭で強み3点と事例を紹介し、巻末に問い合わせ用QRコードを配置すると反応が上がります。
紙は本文をマット系、表紙を光沢コート紙にすることで高級感と視認性を両立。
あるメーカーでは、展示会用冊子を導入して問い合わせ数が1.6倍に増加しました。
冊子は目的別に最適化することで、限られた予算でも最大の効果を発揮します。
印刷会社に相談しながら構成を整えることで、“伝わる1冊”を無理なく実現できます。
FAQ|よくある質問
Q1. PDFで配布するのと冊子で配布するのは、どちらが効果的ですか?
目的によりますが、商談やプレゼンなど“信頼を重視する場面”では冊子のほうが記憶に残りやすく、離脱率も低下します。
Q2. 冊子印刷は最低何部から発注できますか?
小ロット印刷(5部~)から対応可能な印刷会社もあります。遠藤印刷では用途や部数に応じた最適な仕様を提案しています。
Q3. コストを抑えたい場合、どこを調整すればよいですか?
ページ数・紙質・製本方法の見直しで費用を削減できます。モノクロ印刷や中綴じ製本もおすすめです。
Q4. デザインデータがなくても依頼できますか?
Word・PowerPoint・PDFデータからでも冊子化可能です。印刷会社が体裁を整えて仕上げるケースが多いです。
Q5. 納期はどのくらいかかりますか?
仕様にもよりますが、一般的に3~5営業日で納品可能です。遠藤印刷では“急ぎ対応”の相談にも柔軟に応じています。
第5章 まとめ|“伝わる冊子”はコストではなく投資
5-1 費用対効果を高める「冊子=安心を届けるメディア」思考
冊子制作の判断で多くの担当者が迷うのは「コストに見合うのか」という点です。
しかし、印刷は単なる支出ではなく、“伝わる安心を届ける投資”と考えるのが重要です。
紙の冊子は、PDFにはない“記憶に残る手触り”と“視覚の整理効果”を持ちます。
実際に、営業資料を冊子にした企業では再面談率が1.5倍に上がった例もあります(出典:日本印刷産業連合会)。
冊子は「誠実な会社」「きちんと伝える姿勢」という印象を自然に生み、
短期的な販促物ではなく、信頼を積み重ねるメディアとして働きます。
5-2 まずは相談から始めよう――現場対応力のある印刷会社に頼る理由
冊子制作を成功させるには、「最初に相談する」ことが重要です。
印刷会社は、単にデータを印刷するだけでなく、目的に合わせた仕様提案やレイアウト調整を行います。
初めての担当者でも、「用途」「納期」「部数」を伝えるだけで、最適な方法を導き出してくれます。
たとえば、展示会用パンフレットを相談ベースで見直した企業では、
紙質とページ数を調整することで印刷費を20%削減・納期を2日短縮できました。
現場を知る印刷会社ほど、無駄を省き、成果を出す仕様設計が得意です。
5-3 千代田区・飯田橋の遠藤印刷が提供する「法人向け冊子印刷サポート」
遠藤印刷は、千代田区飯田橋に自社工場を構える創業55年の印刷会社です。
データ処理から印刷・製本・納品までをワンストップで対応し、
法人・学会・団体の冊子制作を“相談ベース”で支援しています。
「PDFデータをそのまま冊子化したい」「社内報を定期的に印刷したい」といった依頼にも柔軟対応。
自社完結だからこそ、小ロット・短納期・柔軟対応を実現し、“納品への責任”を何より大切にしています。