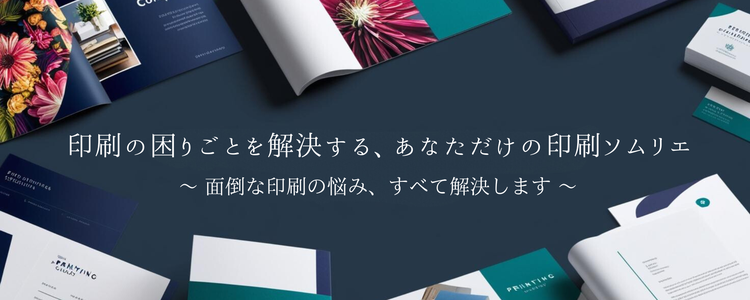【目次】
第1章 少部数印刷とは?どのくらいから「少部数」なのか
- 1-1 「少部数印刷」は何部から?一般的な目安と定義を解説
- 1-2 少部数印刷が可能な理由|オンデマンド印刷の仕組み
- 1-3 少部数印刷が活躍するシーンと用途例
第2章 仕上がりの違いはここで決まる!少部数印刷の品質ポイント
- 2-1 オンデマンドとオフセットの違い|発色・トーン・再現性を比較
- 2-2 紙質と厚みで変わる印象|おすすめの用紙選び
- 2-3 印刷データで仕上がりが変わる|チェックしたい3つの設定
第3章 少部数印刷の費用とコストを抑えるコツ
- 3-1 少部数印刷の費用相場を知る|A4冊子・チラシ・パンフの比較
- 3-2 コストを抑える3つの工夫|紙・納期・データの最適化
- 3-3 ムダをなくす!必要な分だけ印刷する「賢い発注術」
FAQ|よくあるご質問
第1章 少部数印刷とは?どのくらいから「少部数」なのか?
1-1 「少部数印刷」は何部から?一般的な目安と定義を解説
「少部数印刷」とは、必要な部数だけを印刷するスタイルのことです。明確な基準はありませんが、一般的には1部〜300部程度を少部数とする印刷会社が多い傾向です。
オンデマンド印刷を提供するグラフィック社では「10部からの冊子印刷」を公式に案内しています(株式会社グラフィック)。こうした小ロット対応は、展示会配布物や社内パンフレットなど「少しだけ印刷したい」ニーズに最適です。大量印刷が前提だった時代と比べ、現在は少部数でも手軽に高品質な印刷が手軽になってきました。
遠藤印刷では最低2部から発注可能です。
1-2 少部数印刷が可能な理由|オンデマンド印刷の仕組み
少部数印刷を支えるのがオンデマンド印刷機です。
従来のオフセット印刷は「版」を作成するため初期費用が発生し、少部数では割高感がありました。しかしオンデマンド印刷ではデジタルデータを直接プリンターに送信して印刷する方式で、版の作成が不要です。そのため、1部からでも発注でき、納期も短縮されます。オンデマンド印刷は「必要な部数を必要なときに出力できる」環境対応型の方式として普及しています(リコー公式サイト)。また、近年の機種では色再現性が向上し、小ロットでも商業品質を実現しています。
1-3 少部数印刷が活躍するシーンと用途例
少部数印刷は、在庫を持たずに印刷できるため、さまざまな場面で利用されています。
代表的な用途としては、学会資料・論文製本(10〜50部)、会社案内・営業パンフレット(50〜200部)、イベント配布物(100〜300部)などがあります。
「必要な分だけ印刷したい」「頻繁に内容を更新したい」という要望にぴったりです。また、環境省の3R推進資料では「廃棄物削減のためのオンデマンド印刷の活用」が推奨されています(環境省 3R推進資料)。
つまり少部数印刷は、コスト削減と環境配慮を両立できる印刷スタイルといえるでしょう。
第2章 仕上がりの違いはここで決まる!少部数印刷の品質ポイント
2-1 オンデマンドとオフセットの違い|発色・トーン・再現性を比較
少部数印刷では、多くの場合「オンデマンド印刷」が採用されます。
これはデジタルデータをそのまま出力する方式で、版を作らずスピーディに印刷できるのが特徴です。
一方「オフセット印刷」は、アルミ版を介してインクを紙に転写する方式で、色の安定性・グラデーション再現性に優れるため、大量印刷に適しています。
日本印刷産業連合会によると、近年ではオンデマンド印刷の解像度が1,200dpi以上に進化し、色のムラやトーン差は肉眼ではほとんど判別できないレベルに達しています(日本印刷産業連合会)。
つまり、発注初心者の方でも「オンデマンド=低品質」という心配は不要です。
2-2 紙質と厚みで変わる印象|おすすめの用紙選び
印刷物の仕上がりを大きく左右するのが「紙の種類」と「厚み」です。
たとえば、光沢感のあるコート紙は写真やカラーパンフレットに最適で、発色が鮮やかです。
一方で、マットコート紙は反射が少なく、落ち着いた印象に仕上がります。
また、**上質紙(コピー用紙に近い質感)**は筆記性に優れており、アンケートや資料印刷に向いています。
印刷会社のデータでは、A4チラシを90kgのコート紙で印刷した場合、1部あたりの重さは約6.3gとされており、配布用途にも扱いやすい厚みです(株式会社グラフィック)。
初めての方は、「どんな用途に使うのか」を基準に選ぶと失敗しにくいでしょう。
2-3 印刷データで仕上がりが変わる|チェックしたい3つの設定
少部数印刷の品質を最大限に引き出すには、データ設定の正確さが重要です。
特に注意すべきは以下の3点です。
- 解像度(dpi):画像は300dpi以上が推奨。72dpiだと印刷時にぼやける要因。
- カラーモード:RGBではなく、印刷用のCMYKに変換すること。
- 塗り足し設定:仕上がり線より3mm以上余白を確保すること。
これらの設定を守るだけで、印刷トラブルの9割は防げるといわれています(Adobe公式ヘルプ)。
印刷会社によっては、入稿前に自動チェック機能を提供しており、初心者でも安心してデータを準備できます。
第3章 少部数印刷の費用とコストを抑えるコツ
3-1 少部数印刷の費用相場を知る|A4冊子・チラシ・パンフの比較
少部数印刷の費用は、部数・サイズ・仕様によって大きく異なります。同条件で1,000部に増やすと単価は下がりますが、総額は10,000円を超えます。
冊子印刷の場合、A4・16ページの中綴じ冊子を100部制作すると1部あたり約200〜250円が目安とされています。このように、少部数は単価こそ高めでも「総額が低く、在庫リスクがない」点が最大の利点です。
3-2 コストを抑える3つの工夫|紙・納期・データの最適化
少部数印刷で費用を賢く抑えるには、次の3つの工夫が効果的です。
- 紙を軽量にする:90kgから70kgに変更するだけで、印刷代が約10〜15%削減できます。
- 納期を標準納期にする:特急納期は最大30%高くなるため、余裕をもった発注が大切です。
- データを完全入稿にする:印刷会社による修正作業を減らすことで、追加費用を防げます。
また、複数の印刷物を同時に依頼する「同時発注割引」を利用すれば、少部数でもコスト効率を高められます(出典:印刷通販プリントネット)。
3-3 ムダをなくす!必要な分だけ印刷する「賢い発注術」
少部数印刷の最大の魅力は、「必要なときに必要な分だけ印刷できる」柔軟性です。
イベント資料を50部だけ先に印刷し、後日10部だけ追加する「分割発注」も可能です。
オンデマンド印刷を採用している会社では、データを保存しておけば増刷時の対応がスピーディになる傾向があります。
これにより、在庫スペースの確保や廃棄の手間が不要になり、印刷コスト全体を約20〜30%削減できるケースもあります。
少部数印刷は単なる「小ロット印刷」ではなく、企業のコストマネジメントを支える効率的な印刷戦略なのです。
【FAQ】
少部数印刷は何部から対応できますか?
多くの印刷会社では1部から対応可能です。実務上は用途により1〜300部程度を「少部数」と捉えます。 会社案内・イベント配布物・学会資料など、配布対象が限定される印刷物に最適です。
オンデマンド印刷の品質はオフセット印刷より劣りますか?
近年のオンデマンド機は高解像度化により、一般的なパンフ・資料用途では差を感じにくい品質です。 大ロットや特色・厳密な色再現を重視する場合はオフセットが有利なケースもあります。用途と部数で使い分けるのがコツです。
少部数でも紙の種類や加工(PP貼り・箔押しなど)は選べますか?
はい、用紙・厚み・加工は選択可能です。標準はコート/マットコート/上質紙で、表紙PP(グロス・マット)や折り・ミシン・孔開け等の後加工も対応できます。 ただし一部の特殊加工は最低ロットや追加納期が発生することがあります。
納期はどのくらいですか?当日や翌日仕上げは可能ですか?
データが問題ない場合、少部数のチラシや簡易冊子は当日〜2営業日が目安です。 加工や部数が多い場合は3〜5営業日以上かかることがあります。急ぎは事前相談のうえ、入稿締切と校正有無を明確にするとスムーズです。
費用を抑えるポイントはありますか?
- 紙を最適化:厚みを一段階下げる/標準在庫紙を選ぶ。
- 納期に余裕:特急料金を回避。標準納期で依頼。
- 完全データ入稿:RGB→CMYK、画像300dpi、塗り足し3mmでトラブル削減。
- 版下をまとめる:複数アイテムを同時発注し面付け効率を上げる。
再注文(増刷)は簡単ですか?色は同じになりますか?
データを保管しておけば同条件で増刷可能です。オンデマンド印刷は機種や用紙ロット差で、 色がわずかに変動する場合があります。色基準(簡易校正・出力見本)を残しておくと再現性が高まります。