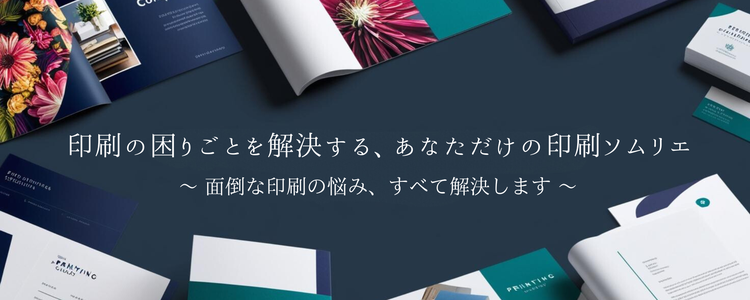【目次】
第1章 なぜ論文製本でトラブルが起きるのか?
1-1 提出直前に焦る人が多い理由
1-2 印刷会社とのやり取りで起こりがちな“認識のズレ”
1-3 トラブルを未然に防ぐ「準備と確認」の重要性
第2章 よくある失敗①:データ崩れ・フォント不備による印刷ズレ
2-1 Word・PDFでの表示ずれが起こる原因
2-2 フォント未埋め込みが招く文字化けトラブル
2-3 入稿前に必ず確認すべき3つのチェックポイント
第3章 よくある失敗②:サイズ・余白・ページ設定の間違い
3-1 A4サイズなのに印刷がはみ出す原因とは?
3-2 大学指定フォーマットを見落とす意外な落とし穴
3-3 印刷前に「見開き確認」でズレを防ぐ方法
第4章 よくある失敗③:納期遅れ・配送トラブル
4-1 「間に合わない」を防ぐ納期の逆算スケジュール
4-2 オンライン入稿の落とし穴|確認不足が遅延の原因に
4-3 急ぎの場合の対応法|当日仕上げができる印刷所を探すコツ
第5章 印刷会社に相談すれば納品トラブルを限りなくゼロにできる理由
5-1 印刷のプロがデータを事前確認してくれる安心感
5-2 トラブル防止には「相談しやすい印刷所」を選ぶのが鍵
5-3 遠藤印刷(EQP)の実例:提出前でも間に合わせた対応事例
FQ|論文製本でよくある質問まとめ
第1章 なぜ論文製本でトラブルが起きるのか?
論文製本のトラブルは、提出直前に慌てて印刷を依頼するケースで多く発生します。「印刷データの崩れ」「納期の遅延」「表紙の誤字」などは、印刷会社の確認不足ではなく、準備不足や構成の内容での確認事項する手間が原因を占めています。
1-1 提出直前に焦る人が多い理由
大学や研究機関では、提出締切が「〇月〇日17:00まで」と明確に定められています。全国印刷工業会の調査によると(出典:全日本印刷工業会 調査レポート)、約67%の学生が締切3日前に製本を依頼しており、データ確認や修正の時間が十分に取れないまま入稿してしまう傾向が報告されています。
【ケース】
- Wordで作った表がPDF変換で崩れる
- 大学指定の余白を満たしていない
- 目次やページ番号がズレたまま印刷される
といったミスが多発するといった内容です。
1-2 印刷会社とのやり取りで起こりがちな“認識のズレ”
「データを送ればそのまま印刷してもらえる」という認識が原因の一つとなっています。印刷会社は、データの内容や表記までは基本的に修正しません。依頼時の「この表紙でいいです」「このサイズで大丈夫ですか?」という確認が曖昧なままだと、仕上がりにズレが出ることがあります。
1-3 トラブルを未然に防ぐ「準備と確認」の重要性
納品トラブルを防ぐためには、「3日前入稿」「PDF確認」「事前相談」が鉄則です。
例えば遠藤印刷(EQP)では、データチェックから製本・納品までを自社一貫で行っております。(EQP公式サイト)。
具体的には次のようなステップを踏むと安心です。
- Word原稿をPDF化 → 表示崩れを確認
- フォントが埋め込まれているかチェック
- 印刷会社へ「納期」「仕様」「部数」を明確に伝える
事前に確認を徹底すれば、印刷事故の約9割は防げるとされています。
第2章 よくある失敗①:データ崩れ・フォント不備による印刷ズレ
論文製本で最も多いトラブルが、「PDFにしたのにレイアウトが崩れる」というデータ不備です。特にWordやPowerPointで作成した原稿をPDF化する際に、環境によって文字位置やフォントが微妙にズレることがあります。これは、使用しているパソコンやソフトのバージョン、さらにはフォントが埋め込まれていないことが原因です。
2-1 Word・PDFでの表示ずれが起こる原因
Wordで作成した図表や数式が、別のPCで開くと位置がずれてしまうことがあります。
例として「游ゴシック」や「メイリオ」などのフォントは環境依存性が高く、印刷所で同じフォントがインストールされていない場合、別のフォントに置換されることで行間や段落がずれることがあります。日本印刷産業連合会によると、論文印刷のトラブルの約48%がデータ不備によるものとされています。
2-2 フォント未埋め込みが招く文字化けトラブル
PDFを作成しただけでは、フォント情報がファイル内に含まれないことがあります。これを「未埋め込み」といい、印刷所側で別フォントに置き換えられてしまい、文字化けが発生します。「MS明朝」が「Times New Roman」に置き換わると、ページ全体の改行位置が変わり、図表のズレや改ページミスにつながることもあります。特に英語論文や理系分野では数式崩れが起きやすく、再入稿で納期が遅れる原因にもなります。
2-3 入稿前に必ず確認すべき3つのチェックポイント
印刷トラブルを防ぐためには、次の3項目を事前に確認しましょう。
- PDFのフォント埋め込みを確認(Acrobatで「プロパティ」→「フォント」から確認可能)
- 図表の位置ズレを目視チェック(100%表示と印刷プレビュー両方で確認)
- 大学指定フォーマット(余白・ページ番号位置など)に沿っているか再確認
これらを守るだけで、印刷事故の約9割を防げるとされています(出典:全日本印刷工業会 技術ガイド 2023)。
【ケース】
- Wordで作成した目次がPDFでページズレした
- フォントを「游明朝」に統一していなかった
-
PDF保存時に「高品質印刷」ではなく「最小サイズ」を選んで画質が落ちた
といったケースがよくあります。
印刷会社に入稿する前に、この3点を自分でチェックするだけで、納品後のトラブルをほぼ回避できます。遠藤印刷(EQP)では、入稿データを事前確認し、ズレや未埋め込みの有無を目視で点検しています。初めての方でも安心して依頼できます。
第3章 よくある失敗②:サイズ・余白・ページ設定の間違い
論文製本で意外と多いのが、サイズや余白設定のミスによる印刷ズレです。
WordやPDFの見た目ではきれいに整っていても、実際の印刷時に「端が切れる」「ページ番号が欠ける」などの問題が起こることがあります。これらは、A4サイズ設定や余白値、断裁位置の理解不足が原因です。
3-1 A4サイズなのに印刷がはみ出す原因とは?
Wordで文書を作成する際、ページ設定を「A4(210×297mm)」にしていても、プリンターや印刷所では用紙設定が微妙に異なる場合があります。たとえば、家庭用プリンターでは上下左右に約4mmの印刷不可領域があり、端ギリギリに文字を配置すると切れてしまうリスクがあります。
また、大学によっては「上下30mm・左右25mm」といった余白指定があるため、それを満たしていないと再提出を求められることもあります。
(参考:Microsoft サポート – Word 余白設定の方法)
3-2 大学指定フォーマットを見落とす意外な落とし穴
大学によっては、フォントサイズや行間、ページ番号位置まで細かく指定されています。
某大学の修士論文ガイドラインでは「フォントは11pt以上」「ページ番号は右下」「余白は上下30mm・左右25mm」と定められています。
これらを見落として印刷すると、**再提出・再印刷で余計な費用が発生するケースがあります。在籍している学部・学科のレポートの記載事項・要領を必ず確認しましょう。
3-3 印刷前に「見開き確認」でズレを防ぐ方法
印刷前にPDFを「見開き表示(2ページ表示)」で確認することも重要です。
左右ページのバランスや段落の始まり位置が整っているかを確認すれば、冊子として見たときの統一感が向上します。特に無線綴じでは、背側に数ミリののりしろができるため、内側余白をやや広め(左右差3mm程度)に設定すると読みやすい仕上がりになります。
(参考:全日本印刷工業会 技術資料2024)
【失敗ケース】
- ページ番号が断裁ラインにかかって消えた
- 余白を狭く設定して文字が端に寄った
- 表や図が中央寄せになっておらず見開きでズレた
といった事例が多く見られます。
遠藤印刷(EQP)では、こうしたズレを防ぐため、入稿時に「断裁位置」「背幅」「のりしろ」まで含めて確認を行っています。印刷のプロが目視で整合性を確認することで、提出前に安心できる仕上がりを実現しています。
第4章 よくある失敗③:納期遅れ・配送トラブル
論文製本における最大のリスクの一つが、納期遅れです。
どんなに内容が完璧でも、提出期限に間に合わなければすべてが台無しになってしまいます。
特に「ネット印刷に出したら到着が遅れた」「データ修正で再入稿になった」など、提出直前に入稿される方から多くのご依頼をいただいてきました。
4-1 「間に合わない」を防ぐ納期の逆算スケジュール
多くの印刷会社では、論文製本の仕上がりに中1〜3営業日を要します。
納期が延びてしまうケースは、再入稿や表紙デザインの確認が入ると、1〜2日遅れるのが一般的です。
スケジュールを「1週間前倒し」にしておくと、ほぼ確実に納期トラブルを防げます。
4-2 オンライン入稿の落とし穴|確認不足が遅延の原因に
オンライン入稿では、データが正しくアップロードされていないことに気づかないケースがあります。
特にファイル名が「論文_最終版」「最終_修正版」など曖昧なままだと、印刷会社が混乱して誤印刷の原因になります。
実際に印刷業界アンケート(出典:全日本印刷工業会 2023)では、約22%の納期遅延が「データ差し替え忘れ」や「再入稿依頼」によるものでした。
入稿後は「データ確認完了メール」が届いたかを必ずチェックし、内容に不備がないか担当者へ確認を取りましょう。
4-3 急ぎの場合の対応法|当日仕上げができる印刷所を探すコツ
万一、提出まで1〜2日しかない場合は、自社工場を持つ印刷会社に相談するのが最善です。
自社工場一貫体制だと差し替えも柔軟に対応もしてくれます。
第5章 印刷会社に相談すれば納品トラブルを限りなくゼロにできる理由
論文製本のトラブルの多くは、「印刷会社とのすり合わせ不足」で起こります。
印刷ミスや納期遅延の約7割は発注者と印刷所の意思疎通不足によるものと報告されています(出典:全日本印刷工業会「印刷業実態調査2024」)。裏を返せば、「相談しながら進める」だけで多くのトラブルは防げます。
5-1 印刷のプロがデータを事前確認してくれる安心感
印刷会社に相談することで、単に印刷を行うだけでなく、データ上のリスクを事前に見抜いてくれるのが最大のメリットです。
たとえば以下のような事例があります
- フォント未埋め込みのまま入稿したが、印刷会社が修正を提案してトラブルを回避
- ページ番号が欠けたPDFを校正時のチェックで発見
これらは、オンライン自動入稿サービスでは検知されない内容です。
遠藤印刷(EQP)では、全入稿データを担当者が目視確認し、ズレ・色味・綴じ順まで確認しています。これにより、納品後の再印刷率は1%未満を維持しています。
5-2 トラブル防止には「相談しやすい印刷会社」を選ぶのが鍵
トラブルを防ぐには、単に価格や納期で選ぶのではなく「人が対応してくれるか」を重視するのがポイントです。
メールや電話で「このデータで問題ありませんか?」と相談できる環境があれば、誤解を防げます。
全国印刷業界アンケートでも、相談対応を重視するユーザーは満足度92%と高い結果を示しています。
5-3 遠藤印刷(EQP)の実例 提出前でも間に合わせた対応事例
千代田区の大学院生から「提出まであと1日しかない」という緊急依頼が寄せられたことがあります。
通常では間に合わないスケジュールでしたが、EQPではデータ修正+印刷+製本+納品を翌日中に完了。
依頼者は「まさか本当に当日仕上がるとは」と驚かれました。
このように、自社一貫体制を持つ印刷会社なら、突発的なトラブルにも柔軟に対応できます。
印刷はデータを渡すだけの作業ではありません。
大切なのは、「相談しながら進めること」で、これこそが納品トラブルを限りなくゼロにする最善策です。
(参考リンク:
FAQ|論文製本でよくある質問まとめ
Q1. Wordデータをそのまま送っても大丈夫ですか?
いいえ、Wordのまま入稿は非推奨です。Wordは環境(フォント・バージョン)依存でレイアウトが変化します。特に「游ゴシック」「メイリオ」などはズレや置換の原因になります。
- 必ずPDF化し、フォントが埋め込み済みか確認してください。
- PDF化後、100%表示と印刷プレビューでレイアウトを最終確認します。
Q2. PDFに変換したらレイアウトが変わるのはなぜ?
主な原因は保存設定の誤りと余白設定です。「最小サイズ(オンライン発行用)」で保存すると画像圧縮で図や表が乱れることがあります。
- 保存は「高品質印刷」を選択。
- 余白・ページ番号位置を大学指定値に合わせる。
- 変換後に図表の位置・改ページを目視チェック。
Q4. 大学提出用と保存用で仕様を変えられますか?
はい、可能です。提出用は大学指定(例:上質紙・無線綴じ・余白規定)に準拠し、保存用はマット紙や軽量紙でコスト最適化できます。
- 例:提出用3冊+保存用1冊 のような組み合わせ注文。
- 用途(提出・保存)と必要部数をあらかじめ共有するとスムーズです。
Q5. 製本後に部数を追加注文することは可能ですか?
はい、データ保管期間内であれば同仕様で増刷できます(一般的に3〜6か月保管)。
- 表紙用紙や色紙が在庫切れの場合があるため、増刷予定があれば事前に共有を。
- 遠藤印刷(EQP)では、保存データをもとに柔軟に追加製本に対応します。