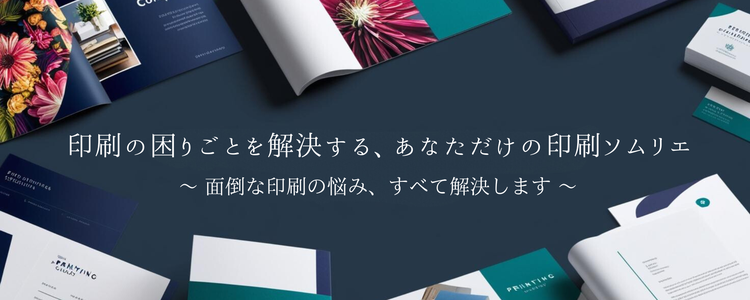【目次】
-
はじめに|背表紙を知ることが本づくりに大切な理由
-
背表紙とは?定義と役割をわかりやすく解説
-
背表紙の基本サイズと厚みとの関係
-
ページ数と紙厚から計算する方法
-
背幅早見表の活用
-
-
背表紙に入れる情報とは?
-
書名
-
著者名
-
出版社やロゴ
-
-
文字方向と配置のポイント
-
縦書き・横書きの選び方
-
日本と海外の違い
-
-
背表紙デザインのコツ
-
読みやすいフォント選び
-
色と背景の工夫
-
-
背表紙がない本や冊子の例
-
ページ数が少ない場合
-
冊子・パンフレットとの違い
-
-
よくある失敗と注意点
-
文字が切れる・読みにくい
-
印刷のずれ対策
-
-
まとめ|背表紙で本の印象が変わる!
1. はじめに|背表紙を知ることが本づくりに大切な理由
本を手に取ったとき、まず目に入るのは「表紙」ですが、書棚に並んだときに人の目に触れるのは「背表紙」です。背表紙には書名や著者名が記され、本の存在を示す大切な部分です。実は背表紙の作り方ひとつで、本の印象が大きく変わります。初心者の方にとっても、背表紙を理解することは本づくりの基本の第一歩です。
東京都千代田区の遠藤印刷が分かりやすく背表紙について解説します。
2. 背表紙とは?定義と役割をわかりやすく解説
背表紙とは、本を閉じたときにページの束をまとめる「背」に貼り付けられた部分のことです。ここにタイトルや著者名が記載され、本を見つけやすくしたり、整理整頓を助けたりします。図書館や書店で本を探すとき、背表紙がなければ目当ての本を見つけるのは困難です。つまり「本の顔」ともいえる存在なのです。
3. 背表紙の基本サイズと厚みとの関係
3-1. ページ数と紙厚から計算する方法
背表紙の幅(背幅)は、ページ数と用紙の厚みで決まります。たとえば、用紙が0.1mm厚で100ページなら「0.1mm × 100ページ ÷ 2ページ(想定:両面印刷) = 5mm」と計算できます。印刷会社によって計算式は異なる場合もありますが、基本的な考え方は同じです。
3-2. 背幅早見表の活用
初心者が自分で計算するのは大変なので、印刷会社の提供する「背幅早見表」を使うのがおすすめです。多くの印刷会社のサイトに掲載されています
背幅早見表(無線綴じ用)
計算式:背幅 = (ページ数 ÷ 2) × 1枚の紙厚(mm)。 下表は代表的な紙厚の想定値で算出した目安です(単位:mm)。銘柄・ロット・湿度などで厚みは変動します。
| ページ数 | 0.08mm/枚 | 0.09mm/枚 | 0.10mm/枚 | 0.12mm/枚 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 1.92 | 2.16 | 2.40 | 2.88 |
| 64 | 2.56 | 2.88 | 3.20 | 3.84 |
| 80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.80 |
| 96 | 3.84 | 4.32 | 4.80 | 5.76 |
| 112 | 4.48 | 5.04 | 5.60 | 6.72 |
| 128 | 5.12 | 5.76 | 6.40 | 7.68 |
| 144 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 8.64 |
| 160 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.60 |
| 176 | 7.04 | 7.92 | 8.80 | 10.56 |
| 192 | 7.68 | 8.64 | 9.60 | 11.52 |
| 208 | 8.32 | 9.36 | 10.40 | 12.48 |
| 224 | 8.96 | 10.08 | 11.20 | 13.44 |
| 240 | 9.60 | 10.80 | 12.00 | 14.40 |
簡易電卓:正確な背幅を出したい場合は、ページ数と紙厚(mm/枚)を入力してください。
背幅:7.20 mm
※ 表紙(カバー)の厚みは通常この計算に含めません。仕上がりのり代や紙銘柄の実測値により±0.2〜0.5mm程度の誤差が出るため、最終データは印刷会社の指定値でご確認ください。
4. 背表紙に入れる情報とは?
4-1. 書名
最も大切なのは書名です。書棚からでもすぐに分かるよう、はっきりと配置します。
4-2. 著者名
書名と並んで重要なのが著者名です。学術書や小説では特に重視されます。
4-3. 出版社やロゴ
出版社や発行元のロゴを背表紙に入れることで、ブランド力を示す効果もあります。
5. 文字方向と配置のポイント
5-1. 縦書き・横書きの選び方
日本の書籍は、一般的に「縦書き」が主流です。
ただし、デザインやジャンルによっては横書きを使うこともあります。
5-2. 日本と海外の違い
海外の本では横書きが多く、文字方向も日本とは逆になることがあります。
そのため、翻訳書などをデザインする際は注意が必要です。
6. 背表紙デザインのコツ
6-1. 読みやすいフォント選び
背表紙は細長いため、読みやすいゴシック体や明朝体を選ぶのがおすすめです。
6-2. 色と背景の工夫
本棚に並んだときに目立つよう、背景色や文字色のコントラストを意識しましょう。
7. 背表紙がない本や冊子の例
7-1. ページ数が少ない場合
ページ数が50ページ以下程度や印刷会社により背幅が3mm以下の冊子は、背表紙がつけられないことが多いです。
7-2. 冊子・パンフレットとの違い
パンフレットや薄い冊子は、中綴じ製本が使われるため背表紙がありません。
背表紙があるかないかで単行本としての認知の差が現れます。
8. よくある失敗と注意点
8-1. 文字が切れる・読みにくい
背幅の計算ミスで文字が切れたり、フォントが小さすぎて読みにくいことがあります。
背幅に対して余裕白を設けましょう。製本するのズレを考慮するとより安心です。
8-2. 印刷のずれ対策
製本工程でのわずかなズレを考慮し、文字やロゴを背の中央に正確に配置することが大切です。
9. まとめ|背表紙で本の印象が変わる!
背表紙は本の存在感を決める大切な要素です。初心者でも基本を押さえれば、読みやすく美しい仕上がりになります。遠藤印刷では、お客様の本や冊子づくりを丁寧にサポートし、背表紙のデザインから印刷まで安心してお任せいただけます。